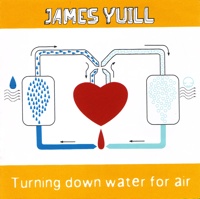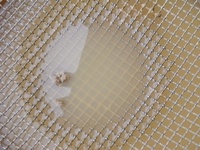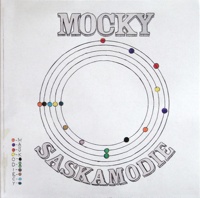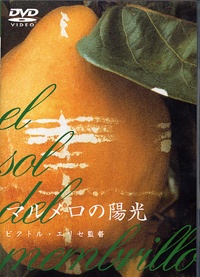ジュネーブのホテルを朝9時に出て、左に葡萄畑、右にレマン湖畔というスイスならではの眺望を楽しみながら列車に揺られること小一時間、小さな町ヴェヴェイに到着。駅で尋ねると、湖畔沿いに歩いて20分くらい、迷うことなく行けることが分かった。この様子だと、約束の時間にはたどり着けそうだ。なにしろ週に一日、水曜日が原則なのに、事前のメールでなんとか金曜の見学を許されたのだから遅れるわけにはゆかない。しばらく歩くと、ネスレ本社ビルを過ぎたあたり、国道と湖に挟まれるような三角地に目的の「小さな家」が目に入る。アルミニウムの外壁に覆われた細長い建物は、なんだかワゴンみたいだ。
身の丈ほどの茶色いドアを開けると、室内に暖気が感じられる。遠来の客としてはうれしい限り。係の女性ジャネッテさんが笑顔で迎え入れてくれると、挨拶もソコソコに室内を歩き回る。なんと幸せな時間だろう。特徴的な11mの横に長いガラス窓からはキラキラと陽光が湖面に反射し、彼方にアルプスが遠望できる。ここで、コルビュジエは母との時間をゆっくりと過ごしたに違いない。朝日を取り入れる高窓、仕切をスライドさせるとゲストのためのベッド、兄と2人で滞在するための秘密の小部屋(?)、愛犬のためののぞき窓、屋上緑化。随所に細かな工夫が凝らされて、ジャネッテさんの説明がひとつひとつの謎を解いてくれるようだ。家というものは、必ずしも広ければいいというわけではない。狭小であっても、日が良く当たる庭があって、必要にして充分な設備さえあればいい。
ほぼすべてがオリジナルの状態というのも嬉しかった。しかも、どこを触れてもOK。もちろん椅子に座ることも許されている。で、置いてあるLCシリーズの椅子もオリジナルですか、と質問したところ、2脚のうちの1脚だけがそうだとのこと。言われてみれば、確かに細部に違いがある。すると、ジャネッテさんが持ってみろというジェスチァーをした。持ち上げると、軽い。イームズのLCWやDCWもそうだけど、オリジナルといわれるものはリプロダクトに比べると、かなりの度合いで重量が軽い場合が多い。それはちょっとした感動ですらある。
実を言えば、僕はかねてからコルビュジエについて回る「巨匠」という字が苦手だった。だからこそ、この「小さな家」に来て良かったと思う。快適さとは、ある種の軽さなのかもしれない。
 オーラブル・アルナルズ / ファウンド・ソングス
オーラブル・アルナルズ / ファウンド・ソングス